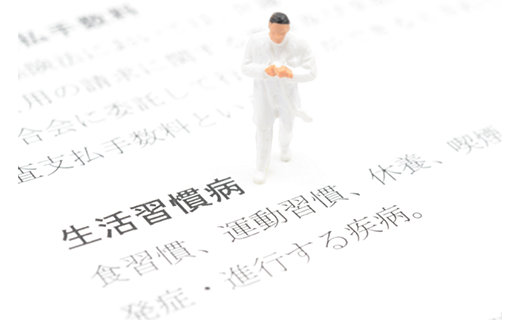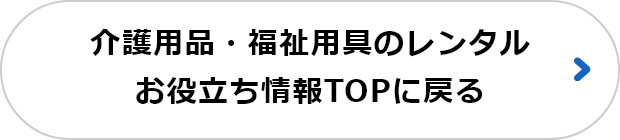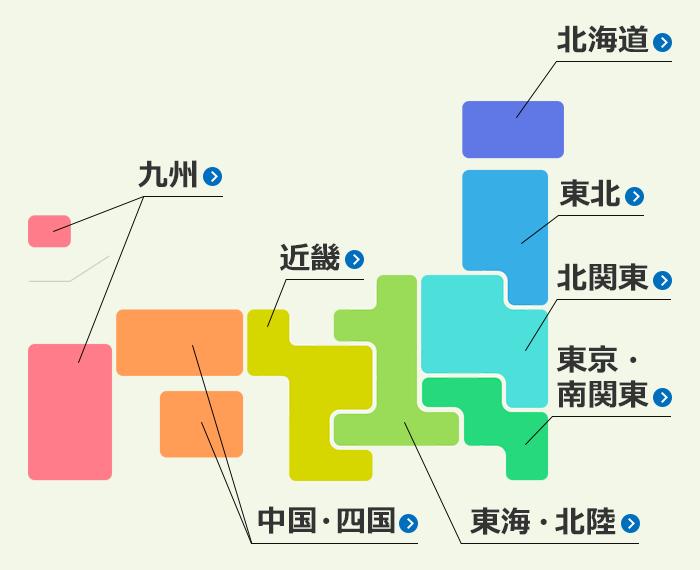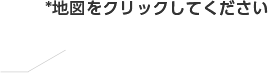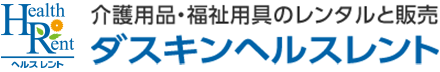-
ホーム
-
商品を探す
-
店舗を探す
-
ご利用案内
-
介護のお役立ち情報
-
採用情報
-
加盟店募集
-
おすすめ商品・特集一覧
-
ケアマネジャーさん向けページ
-
公式SNS
-
お問い合わせ
-
サイトについて
ホーム> 介護のお役立ち情報> 介護用品・福祉用具のレンタルお役立ち情報> 歩行器・歩行車の種類と選び方をわかりやすく紹介!
介護用品・福祉用具の
レンタルお役立ち情報
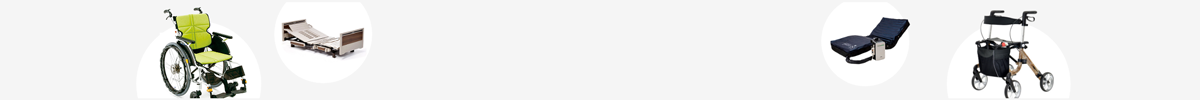
介護用品・福祉用具の
レンタル
お役立ち情報
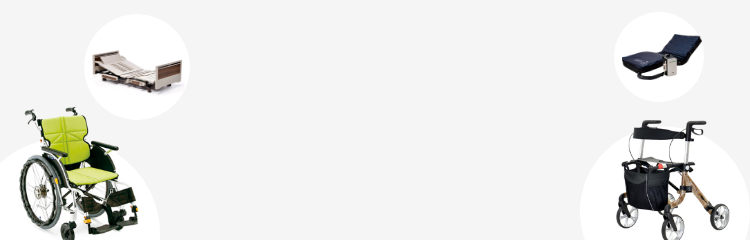
歩行器・歩行車の種類と選び方をわかりやすく紹介!

加齢やケガなどの理由で歩行に不安がある方にとって、歩行器・歩行車は頼りになる存在です。しかし、たくさんの種類があるために、どれを選べば良いかわからないという方も少なくありません。
この記事では、歩行器・歩行車の特徴を紹介したうえで、それぞれの種類を詳しくご紹介します。歩行器・歩行車を検討しているけれど選び方がわからないときにはぜひ参考にしてください。
歩行器・歩行車とは?

歩行器・歩行車は、自力歩行が難しい方をサポートするための歩行補助具です。使用方法やハンドルの形状などから、さまざまな種類の製品が存在します。
一般的な分類として、車輪が付いていないものを歩行器、車輪付きのものを歩行車とするケースが多いようですが、すべてに該当するわけではありません。また、歩行器・歩行車ともに一般的に使われている名称ではあるものの、介護保険対象の区分ではどちらも「歩行器」として扱われています。
ご利用者さまが体重を預けて歩行できる丈夫な設計や、介護保険を利用したレンタルが可能な点が大きな特徴であり、シルバーカーとの相違点です。シルバーカーとの違いについて詳しくは、別記事内で紹介しています。併せて参考にしてください。
歩行器・歩行車の種類
歩行器・歩行車は、さらにさまざまな種類に分類されます。より快適にご利用するためには、種類ごとの特徴を知っておくことが大切です。
歩行器の種類
歩行器はおもに以下の4種類に分類され、それぞれ使用方法が異なります。
ピックアップ歩行器

安定性の高さが特徴のピックアップ歩行器は、固定型歩行器と呼ばれることもあります。
固定された左右のフレームを握り、歩行器全体を持ち上げて前進させ、それを追うように歩きます。どちらかの足に痛みがある場合には、痛みがある側の足から踏み出すことで、歩行器に体重をかけられ負担を軽減できるのがポイントです。
なお、段差では安定性を失いやすいため注意が必要です。
交互型歩行器

交互型歩行器は、左右のフレームがそれぞれの動きをするタイプの歩行器です。
片側のフレームを前方に押し出し、動かしたフレームとは反対側の足を踏み出して歩きます。その後は、手と足の左右を替えながら一連の動きを交互に繰り返すだけです。
ピックアップ歩行器と比べるとバランスを保つのが難しいため、スムーズに歩けるまでに少し時間が必要かもしれません。
車輪付き歩行器(2輪タイプ・4輪タイプ)
ピックアップ歩行器のような固定されたフレームで、脚に車輪が付いているタイプの歩行器です。車輪の数によって、さらに前輪歩行器(2輪タイプ)と四輪歩行器(4輪タイプ)に分類されます。
前輪歩行器は、前脚2脚だけに車輪が付いたタイプ。ご利用者さまは後脚を持ち上げて前輪を進め、フレームに体重をかけることで後輪のストッパーを作動させ、安定した歩行が可能になります。4脚すべてを持ち上げる必要があるピックアップ歩行器よりも簡単に進める点もポイントです。
4脚すべてに車輪が付いているタイプは、四輪歩行器と呼ばれます。四輪歩行器は持ち上げる必要がないため、前進や方向転換がスムーズに行えることが大きな特徴。後輪にストッパーが付いていることが一般的ですが、一度に進めすぎないよう注意が必要です。
立ち上がり歩行器

立ち上がり歩行器は、フレームの高さが2段式になっているタイプです。椅子やトイレから立ち上がるとき、また腰をかけるときにも役立ちます。車輪はなく安定性が高く、歩行時にはピックアップ歩行器と同様に使うことが可能です。
歩行車の種類
歩行車は、基本的に4脚すべてに車輪が付いています。持ち手の形状によって以下の2種類に分類されることが一般的です。
ハンドル型歩行車
自転車のようなグリップ型のハンドルを左右に備えているタイプです。
保持したハンドルの内側に身体を寄せることで、安定感を保ちながら歩行できます。ハンドルにはブレーキも付いているので、速度調整をしながら無理のないペースで歩けるのもポイントです。
馬蹄型歩行車

馬蹄型歩行車は、ご利用者さまを囲むようなハンドルの形が馬蹄(=ばてい:馬の蹄を守る装具)に似ていることからこのように呼ばれています。ハンドルの形状によっては、「U字型」「コの字型」などと表されることも。
ハンドルの前面に体重をかけることで車輪を動かし、前進します。
歩行器・歩行車を選ぶときのポイント
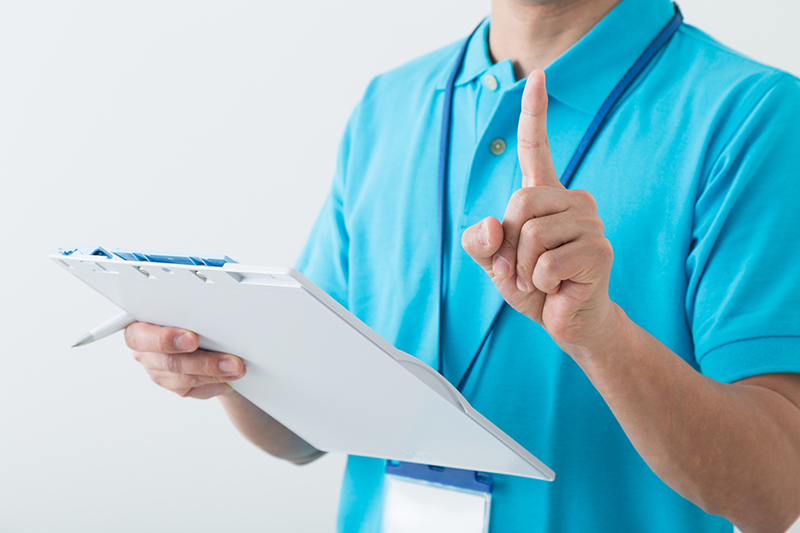
豊富な種類のなかから歩行器・歩行車を選ぶのは難しいという方も少なくないでしょう。ここでは、歩行器・歩行車を選ぶときの重要なポイントを3つご紹介します。
1.ご利用者さまの身体に合うものを選ぶ
歩行器・歩行車の種類を決める際は、必ずご利用者さまが試してみることをおすすめします。
まったく同じ身長の方でも、使いやすいハンドルの高さや形状はそれぞれ異なります。筋力や痛みのある場所などには個人差があるため、近しい人であっても本人以外が想像だけで選ばないようにしてください。
さまざまなタイプの歩行器・歩行車を試し、より快適に歩行できるタイプを探しましょう。
2.利用シーンを想定して選ぶ
歩行器・歩行車をご利用するのはどのようなときで、どのような場所か、具体的なシーンを想定して選ぶことも重要です。
例えば、歩行器は段差がない屋内での利用に向いているため、施設や病院などでのリハビリをおもな利用目的とする場合に選ばれています。
一方で歩行車は、屋外利用に向いていて、多少の段差を乗り越えることも可能です。同じ外出目的でも、長い距離を歩くのか、一時的に折りたたんで車やバスで運ぶケースがあるか、なども考えておくとよいでしょう。
3.便利な機能で選ぶ
ご利用するシーンによって、適切なサイズや重さ、必要な機能は異なります。
歩行器・歩行車にはさまざまな機能を備えたタイプがあり、必要に応じて選ぶことで、より快適に生活できるようになります。代表的な機能は、以下のようなものです。
- ● 折りたたみ機能
- ● 腰かけ機能
- ● 収納機能
- ● 抑速機能
- ● 電動アシスト機能
コンパクトに折りたたむことで、車に積んだり、公共交通機関に乗せたりして運搬できます。持ち運びやすいように軽量なタイプが一般的です。
長い距離を歩く際にいつでも休憩がとれるよう、座面を備えたタイプです。
収納スペースを備えたタイプは、買い物で増えた荷物の運搬などに役立ちます。
速度を調整しながら歩行したい、下り坂での加速が心配という方には、抑速機能付きのタイプがおすすめです。
加速や減速の際に電動でアシストしてくれる機能を備えたタイプなら、ご利用者さまへの負担が大きい坂道でも安心です。
まとめ
歩行器・歩行車は、自立歩行が困難な方の体重も支えられる丈夫な設計が特徴の歩行補助具の一つ。どちらも多様な種類があるため、利用シーンや機能などから適切なものを選ぶことが大切です。また、ご利用者さまが実際に試してみて、より快適に使えるものを選ぶようにしてください。
介護保険を利用したレンタルが可能なため、ケアマネジャーや福祉用具の貸与(レンタル)事業所に相談しながら選ぶのもよいでしょう。
本サイト「ダスキンヘルスレント」では、本記事内で紹介した4種の歩行器(持ち上げ型・交互型・車輪付き・立ち上がり)および2種の歩行車(ハンドル型・馬蹄型)についてお取り扱いをしています。
介護保険の利用ももちろん可能ですので、気になる商品についてぜひお問い合わせください。
介護用品・福祉用具
福祉用具のレンタルについて