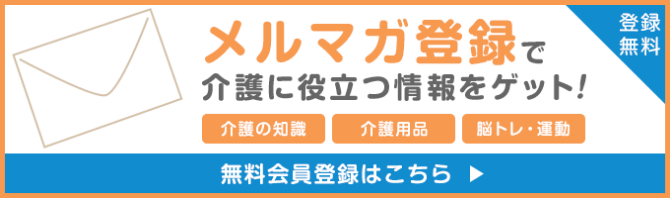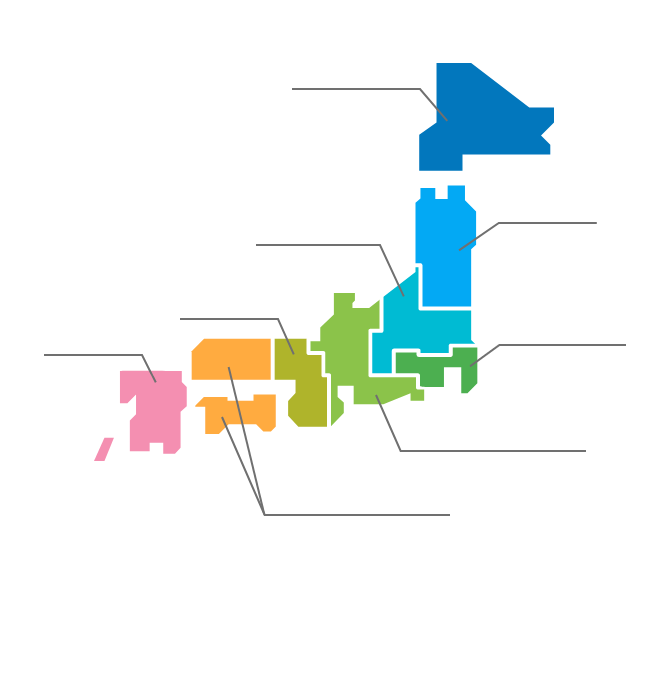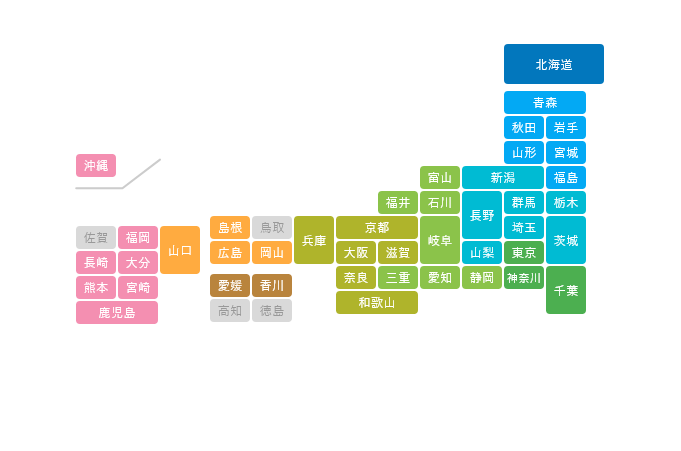-
ホーム
-
商品を探す
-
店舗を探す
-
ご利用案内
-
介護のお役立ち情報
-
採用情報
-
加盟店募集
-
おすすめ商品・特集一覧
-
ケアマネジャーさん向けページ
-
公式SNS
-
お問い合わせ
-
サイトについて
新着コラム
コラム記事一覧
全て
生活と健康
介護・福祉用具
脳トレ
レシピ
ケアマネさん向け
店舗検索
Search Store
地図をクリックしてください
店舗検索
Search Store
地図をクリックしてください