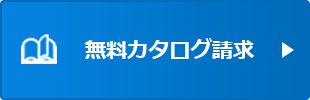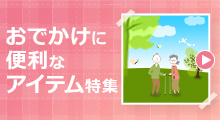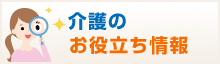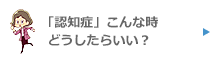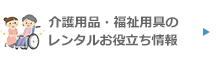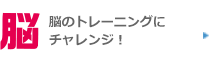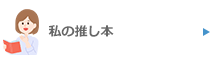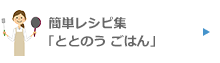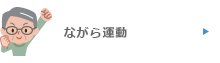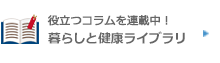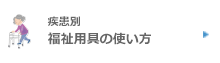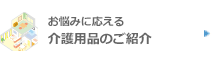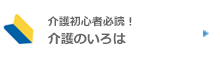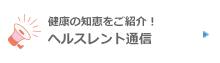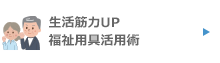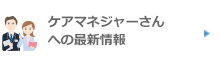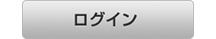-
ホーム
-
商品を探す
-
店舗を探す
-
ご利用案内
-
介護のお役立ち情報
-
採用情報
-
加盟店募集
-
おすすめ商品・特集一覧
-
ケアマネジャーさん向けページ
-
公式SNS
-
お問い合わせ
-
サイトについて
ホーム>介護のお役立ち情報>暮らしと健康ライブラリ>健康づくりに役立つ入浴の5つの作用(前編)
健康づくりに役立つ入浴の5つの作用(前編)

一日の終わりに、ゆっくりとお風呂に入ると身体がポカポカと温まり、疲れがすっきり取れ、快眠にもつながります。また、身体や髪の毛を洗うと清潔さを保つだけではなく、さっぱりとして気分がよくなります。このように入浴は、私たちの心身の健康につながります。それでは、入浴は健康づくりにどのように役立っているのでしょうか。そこには、さまざまな入浴の作用があるようです。ここでは健康につながる入浴の5つの作用について紹介します。
入浴の5つの作用
入浴には、身体によい5つの作用があります。まずは、その中でも特に大切な3つの作用について紹介します。
1.温熱効果

お風呂に、ゆっくり浸かると身体の表面が温まります。すると、皮膚の毛細血管や皮下の血管が広がり、温められた血液が全身を巡って身体全体が温まり、全身に酸素や栄養が運ばれます。
また、身体が温まることで筋肉のコリや関節の痛みが緩和されたり、精神的にもリラックス効果が得られたりします。さらに、免疫機能の向上や自律神経のコントロール、内臓の働きを助ける効果もあります。腎臓の働きもよくなり、利尿作用も高まります。シャワーでは、このような効果は少ないことが分かっています。
なお、お風呂の温度によって身体に与える効果が異なります。目的に応じて、お湯の温度を変えてみてください。
●活動的になりたいときは…
42~44℃のお湯に入ると、交感神経の緊張を促し、活動的になります。
●リラックスしたいときは…
35~38℃のお湯に入ると、副交感神経が働いて落ち着いた気分になれます。
2.水圧作用

お湯に入ると、身体に水圧がかかります。肩まで、お湯に浸かった状態で、お腹まわりを測ると3〜6cm、胸まわりは1〜3cm小さくなります。これは水圧によって身体が締め付けられているからです。
また、お腹に受ける圧力で横隔膜(肺とお腹の境にある膜)が押し上げられ、肺の中の空気の量が減少します。それを補おうとして呼吸数が増え、静脈の血液やリンパ液が心臓に戻り、心臓の働きが活発になって全身の血行が良くなります。さらに、足にたまった血液が心臓に戻って働きを活発にし、血液の循環を促進します。
3.浮力作用
水にモノが入ると、浮き上がろうとする「浮力」がかかります。重い船が水に浮くのは、浮力があるためです。肩まで水に浸かると、浮力によって体重が約1/9になります。それによって身体を支える力が少なくなるため、緊張した筋肉がほぐれます。
ヘルスレント関連コラムリンク
参考サイト:
日本浴用剤工業会
https://www.jbia.org/knowledge4.html
監修:医療法人延寿会 ひるずクリニック
院長 西川泰章