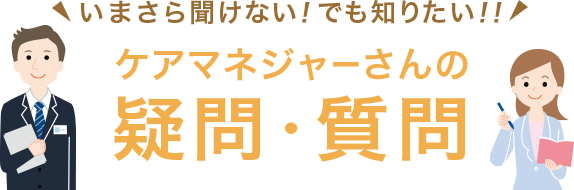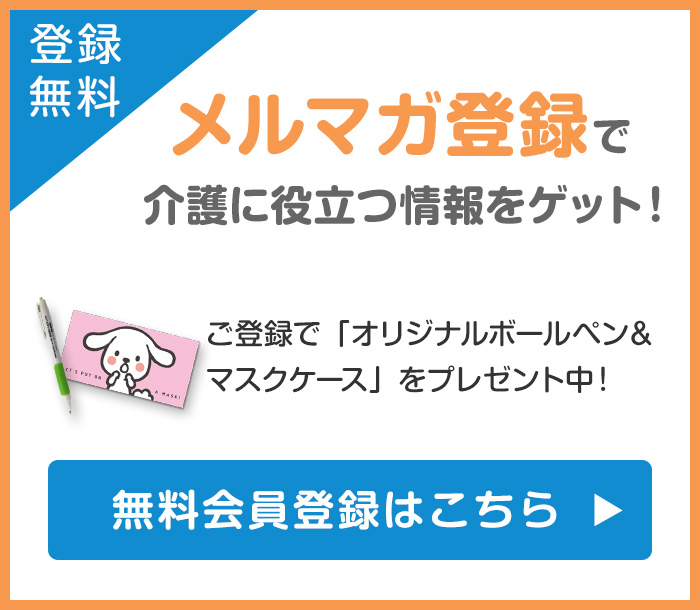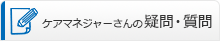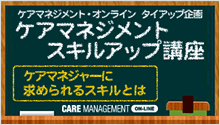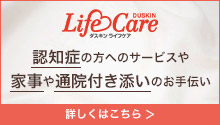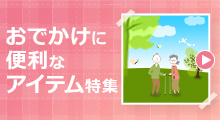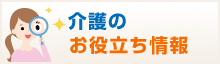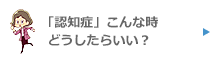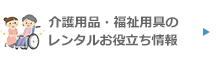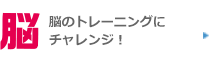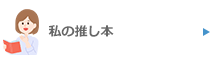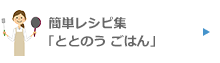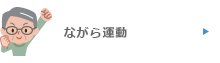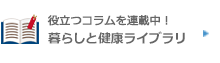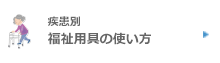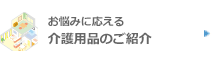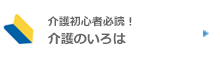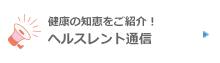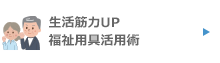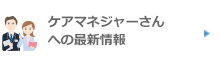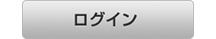-
ホーム
-
商品を探す
-
店舗を探す
-
ご利用案内
-
介護のお役立ち情報
-
採用情報
-
加盟店募集
-
おすすめ商品・特集一覧
-
ケアマネジャーさん向けページ
-
公式SNS
-
お問い合わせ
-
サイトについて
ホーム>介護のお役立ち情報>ケアマネジャーさんの疑問・質問>アセスメントに関する疑問
第1回アセスメントに関する疑問
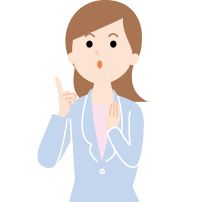
ご利用者がどんな課題を抱えているか、どのように聞き取るか、どのようにまとめるか、迷うことは多いと思います。アセスメントに関する疑問やお悩みにお答えします。
Q1. アセスメント力をつけたいのだが、どうすればいいの?
アセスメントが不十分で、作成中に不明点が出てきます。再度のアセスメントが必要になることがよくあります。
A1. アセスメントの原点に立ち返りましょう。
アセスメントの原点は、ご利用者がどんな課題を抱えているか、これまでどんな生活をしてきて今に至っているのかを把握することです。
アセスメントのポイントご利用者の課題やニーズを具体的に把握していきましょう。把握できたら、それらを整理していきましょう。整理の仕方として、すぐに解決するべきことと、時間をかけて解決するべきことに分けてみることも、いいやり方です。
Q2. アセスメントには、長い時間が必要なの?
ご利用者のニーズを聞き出すために、すごく時間がかかってしまいます。
A2. アセスメントにかける時間は、1時間程度を基本としましょう。
相手の話にじっくり耳を傾けることも大切ですが、長すぎるとご利用者の負担にもなりかねません。アセスメントにかける時間は1時間程度を基本としましょう。
よりスムーズに進めるためにまた、アセスメントの終わりには、次の訪問日を決めるようにしましょう。合わせて「次回に確認させてほしいこと」も伝えましょう。
Q3. 面接技法というほどではないが…
ご利用者やご家族とのスムーズな会話のもって行き方に自信がない。特に、最初から他人事のようなご家族との付き合い方のコツを教えてほしい。
A3. 非協力や無反応の原因となっている本人や家族の心情は何かを思いやることが大事。
質問や提案に反応がない、家族に同席を依頼してもよい返事が返ってこない…。そういう時、「この利用者(家族)は協力的でない」と即断するのは、ケアマネジャーとして正しい態度でしょうか。まずは、その原因となっている本人や家族の心情は「何か」を思いやることが大切です。
そのヒントは、アセスメントにあります。おざなりの問答ではなく、その人についての情報をきめ細かく収集し、利用者と家族の困りごとを明確にする。明確になった両者の意見を照らし合わせ、ケアマネジャーが客観的な意見を加える。そのプロセスにこそ、利用者や家族にいかに向き合っていくかという解答があるのです。
アセスメントに大切なことは現状を理解し、相手の痛みに寄り添い、プロの視点で問題点を明確にし、解決策を提示する。そうした時に初めて「支援するためのヒントをいただけませんか?」という言葉が相手に届くのではないでしょうか。
Q4. アセスメントをどこまで記録に残すべき?
すべてを記録すると膨大な量になってしまい、どこまで記録として残すか、いつも迷っています。
A4. 必要情報が整理され、不要な内容やあいまいな表現がないか確認を。
記録の量が多いということは、アセスメントで課題を把握する能力が高いケアマネジャーと思われます。アセスメントこそ、ケアマネジャーの仕事の醍醐味であり、その成果をたくさん記録に残したいところです。とはいえ、ボリュームが多くなり過ぎるのも困りもの。必要情報が整理されていなかったり、重複した内容や不要な情報まで含んでいる可能性もあります。
記録のポイントやはり、アセスメントの記録には整理が必要です。確認しておきたい主なポイントは以下の2点。
- ●必要な情報が整理されているか
- ●不要な内容がないか
具体的には、
- ●短い文章ですっと読めるか
- ●主語が明確か
- ●情報に洩れがないか
- ●あいまいな表現がないか
などを見ていきましょう。
内容がきちんと頭に入るならば大丈夫。回りくどく感じるのならば、文章の書き方を工夫する必要があります。
改善策メモ用紙などに箇条書きにして、要点を整理してみましょう。個人情報に配慮しつつ、声に出して読んでみること、同じ事業所の他のケアマネジャーに読んでもらうことも効果的でしょう。
<前の疑問・質問
疑問・質問の一覧
その他の読み物一覧
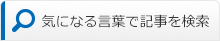 気になる言葉で記事を検索
気になる言葉で記事を検索
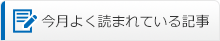 今月よく読まれている記事
今月よく読まれている記事-
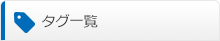 タグ一覧
タグ一覧-