いざというとき、
どう動く?初動の心得。
それを肝に銘じて、親が元気なうちに
確認しておきたい「基本のキ」。
親が高齢になると、そろそろ介護が必要なのでは……と心配になる人は多いはず。一般的に、どんなきっかけで介護が始まるのだろう。
「厚生労働省の2022年の調査によると、その3大原因は『認知症』『脳血管疾患(脳卒中)』『骨折・転倒』です。これらにより自立した生活を送ることが難しくなったときに、介護が始まります。そのほかにも、足腰が弱って買い物が困難になるなど、加齢による衰えによって介護が必要になることもあるでしょう。親が健康に見えても、80歳を過ぎたら、以前できたことができなくなっていないか、観察することが大切です。それが、介護が必要かどうかの見極めに役立ちます」と介護・福祉系ライターの浅井郁子さん。
介護との向き合い方の基本は、家族が抱え込まず、公的機関を適切に頼ることだという。「日本の介護保険制度は充実しています。プロに任せたほうが親自身がラクですし、家族も無理なく自分の生活と両立できますよ」浅井郁子(あさい・いくこ)さん介護・福祉系ライター親の介護をきっかけに、介護に関わる仕事を行うように。おもな活動は、介護にまつわる著書の出版や、記事の執筆など。
介護が必要かも?と思ったら、
まずは地域包括支援センターへ。親が病気やケガをしたり、衰弱で日常生活に支障があったりと、「介護が必要かも?」と思ったときは、どこに相談すればよいのか。「まずは地域包括支援センター(通称・包括)にアクセスしましょう。包括とは、高齢者やその家族から、介護や福祉に関する相談を受ける機関で、全国の中学校区に1つの割合で設置されています。介護が必要かどうかの相談ができて、必要となれば介護サービスを受けるための介護保険申請の手順を教えてくれる。介護初心者にとって心強い存在です」(浅井さん)
包括の利用は基本的に65歳以上を対象としていて、無料で相談可能。連絡先は、各市区町村の役所かホームページで確認を。「包括に在籍しているのは、ケアマネジャー(主任介護支援専門員)、社会福祉士、看護師、保健師など。それぞれの専門分野を生かして、相談者の支援にあたっています」
なかでも中核を担う存在がケアマネジャー。「包括のケアマネジャーは、介護の総合相談窓口であり、地域のさまざまなサービスの種類や利用の仕方について相談できます。また、介護認定で要支援が出た人が利用できる介護予防サービスの『ケアプラン』を作ります」 相手は介護のプロ。窮状を共有するだけでも安心できる。
相手は介護のプロ。窮状を共有するだけでも安心できる。介護保険制度や
介護サービスについて、
基礎的な知識は事前に学ぼう。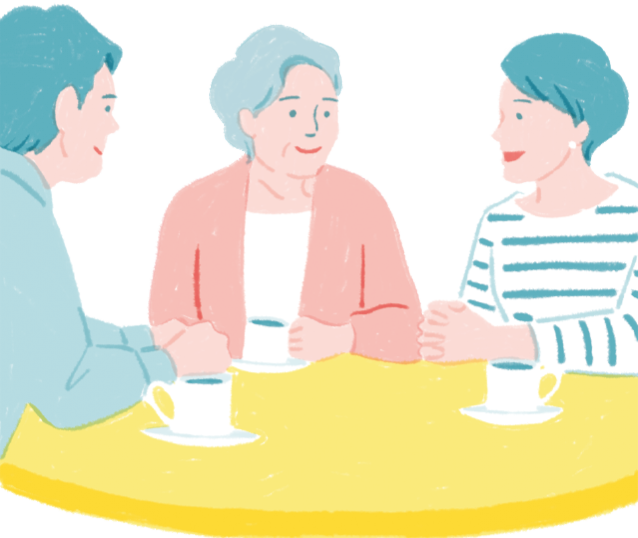 どんなサービスが必要か、
どんなサービスが必要か、
本人の希望も聞いておこう。いざというときに慌てないためにも、介護保険制度の仕組みや、どんな介護サービスを受けられるのか知っておくことが大事。「介護保険制度は、健康保険などと同じく社会保険の一つです。65歳以上の人は、その制度で介護サービスを利用できます。ただし、利用には市区町村の役所による要介護、または要支援の認定が必要」(浅井さん)
介護サービスのメリットは、自己負担額1~3割でサービスを利用できること。「その種類は以下の5つ。在宅や通所など、さまざまなサービスが受けられます」5つのサービス
自宅で暮らしながら利用できるサービス。ホームヘルパーによる掃除などの生活援助や、入浴支援などの身体介護。施設に通うデイサービスも居宅の一つ。
介護が必要になっても、できるかぎり住み慣れた地域で暮らすためのサービス。夜間の巡回訪問や、施設への通所を中心に訪問と宿泊も兼ねたサービスなどがある。
介護用品をレンタル・購入できるサービス。対象は、車椅子や歩行器、介護ベッド、ポータブルトイレなど。レンタルは介護度により利用できるものが異なる。
自宅で安全に暮らせるように、段差の解消など改修を行った際に受けられるサービス。基本的に、改修にかかった費用の9割が支給される。限度額は20万円。
施設に入所して24時間介護を受けるサービス。終身利用が可能な特別養護老人ホームや、医療ケアを受けながら在宅復帰を目指す介護老人保健施設などがある。
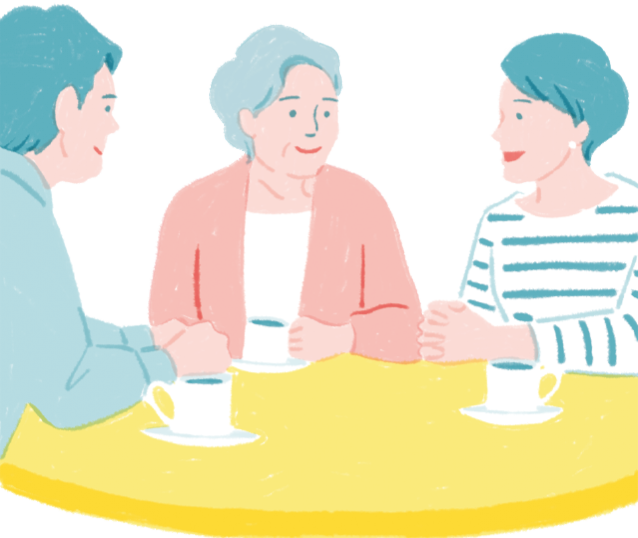 どんなサービスが必要か、
どんなサービスが必要か、
本人の希望も聞いておこう。親の介護は「親のお金で」が基本、
介護に必要なお金の目安も確認を。介護サービスを利用するとなると、やっぱり気になるのが金額のこと。
「年金のみで生活している人は、概ね自己負担額1割で利用可能です。左表が1カ月あたりの自己負担額の上限で、要介護1なら1万6,765円。おおよそ親の年金で賄える額ではないでしょうか。ただし、現役並みに所得がある人の負担額は2~3割になります」(浅井さん)
介護にかかるお金は、親の財布でやりくりするという考え方が理想的。「いずれ自分たちも介護を受ける立場になるということを考えると、親への金銭的な援助はできるだけ抑えたいところ。そのために、まずは親の年金支給額や貯蓄額を把握して、どれくらい介護サービスに回せるのか計算してみましょう。足りない分を家族が負担する場合は、モメごとにならないように、事前に話し合っておくこと」在宅サービスの1カ月あたりの
支給限度額と
自己負担限度額 上記は、1単位=10円の地域の場合の例です。地域によって金額が異なる場合があります。
上記は、1単位=10円の地域の場合の例です。地域によって金額が異なる場合があります。
厚生労働省「サービスにかかる利用料」より「支給限度額」とは、要介護度別に利用できるサービスの上限額。収入に応じて1~3割が自己負担となる。支給限度額を超えて利用することもできるが、その分は全額自己負担になるので要注意。
まずは親の住む場所の『地域包括
支援センター』だけでも確認してお
いて。力になってくれます」
(新田さん)



