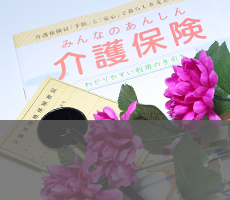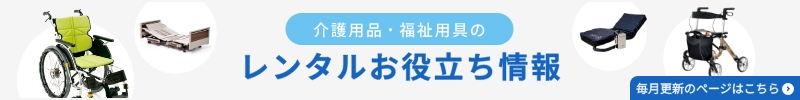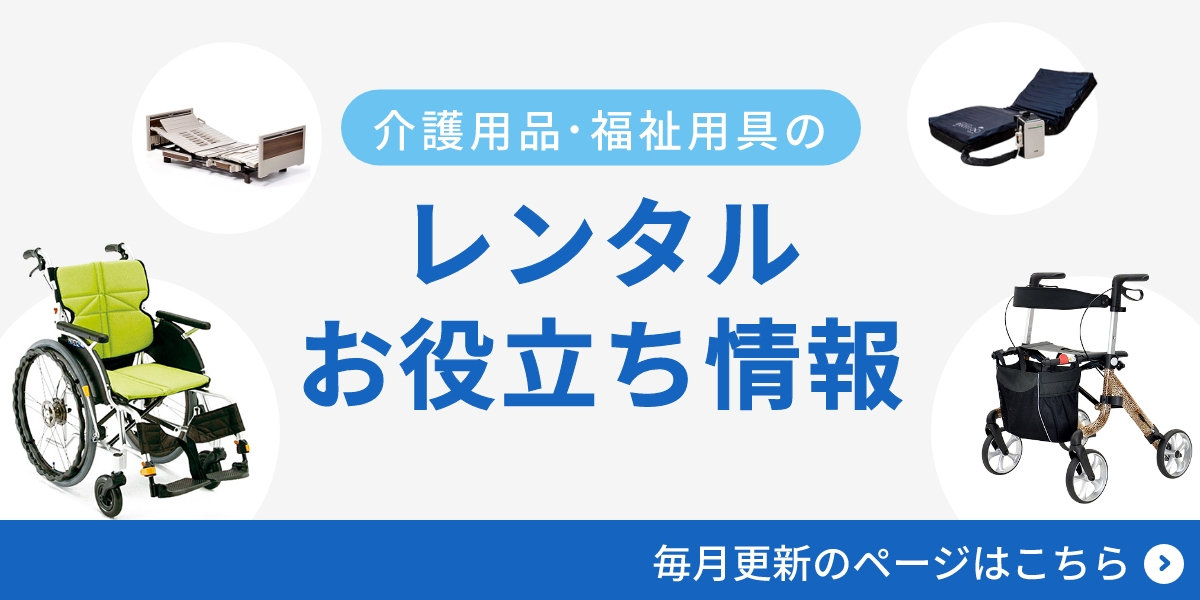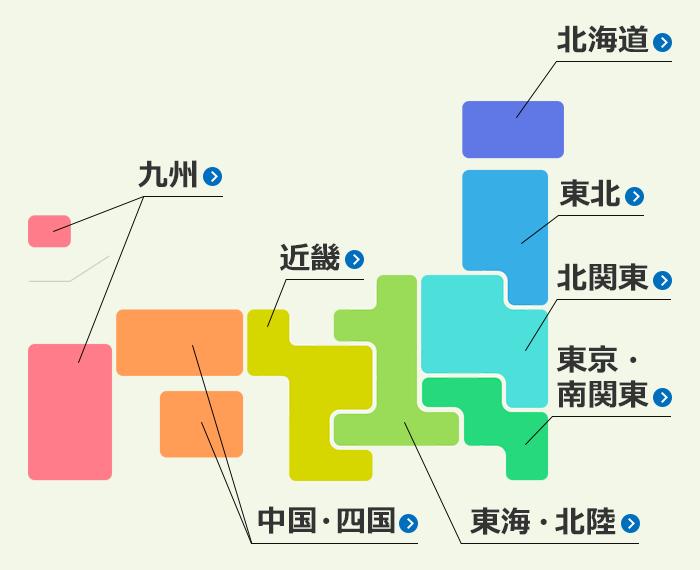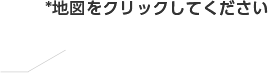介護のお役立ち情報
新着コラム
コラム一覧
キーワード一覧
キーワード検索
カテゴリー
介護用品・福祉用具のレンタルお役立ち情報
おすすめ商品・特集
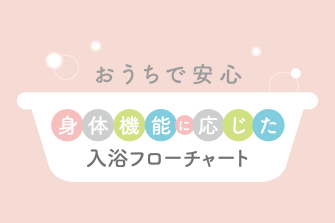
おうちで安心入浴フローチャート。身体機能別に3タイプをご紹介
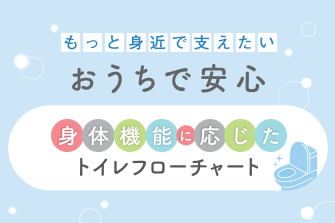
おうちで安心トイレフローチャート。身体機能別に3タイプをご紹介
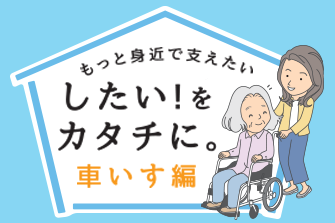
あなたはどのタイプ?
身体状態や環境、目的別に車いすをご紹介
環境づくりからはじめる転倒予防
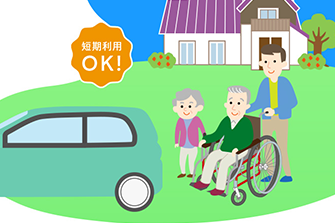
短期利用もOK!
軽量・コンパクトな車いす特集
おでかけに便利な
アイテム特集
介護用品の
衛生対策
快適な座り心地と適切な座位保持を追求した、制菌仕様で衛生的な車いす

軽い!洗える!
HRオリジナルクッション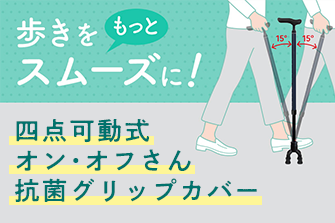
歩きをスムーズに!
便利な四点杖をご紹介
肌ざわり、なめらか。あんしん3層スムース防水シーツ
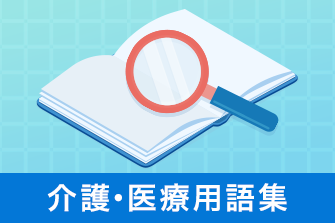
介護・医療に関する専門用語や名称などを分かりやすく解説

介護用品のレンタルや利用について動画で解説